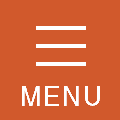ページ内目次
第17回ホスピタル・プレイ・スペシャリスト、国際シンポジウムが、2月8日(土曜日)に開催されました。
今年度は、「子ども時代を保障するホスピタル・プレイー子どもの幸せを学ぼう、考えよう、創造しよう-」と題して、海外の研究者、実践者と、日本人研究者、そして当事者である子ども自身も参加し、子どものウェルビーイングについて考えました。こども家庭庁のアドヴァイザーにもお越しいただき、子どもの声を聴くことに大切さ、子どもの声を施策に反映させる必要性などを学びました。全国から 111名の参加者があり実り多いシンポジウムとなりました。
今年度は、「子ども時代を保障するホスピタル・プレイー子どもの幸せを学ぼう、考えよう、創造しよう-」と題して、海外の研究者、実践者と、日本人研究者、そして当事者である子ども自身も参加し、子どものウェルビーイングについて考えました。こども家庭庁のアドヴァイザーにもお越しいただき、子どもの声を聴くことに大切さ、子どもの声を施策に反映させる必要性などを学びました。全国から 111名の参加者があり実り多いシンポジウムとなりました。
学生からの感想
悪天候に見舞われましたが、全国から111名の方が参加してくださいました。
松平ゼミの学生5名(社会福祉学科社会福祉専攻1年生)も参加し、海外の研究者の最新の研究を聴く機会となりました。
学生の感想を紹介します。
ホセ・マルケス先生(英国)の日本の思春期ウェルビーイングの分析結果に関心を持ちました。思春期の子どもに対する家族からの精神的なサポートが重要とのことでした。一方で、ウェルビーイングの形成に社会的経済格差の影響は小さいとありましたが、私は家族からの精神的なサポートの必要性を高める要因の一つに社会的経済格差が影響している場合もあるのではないでしょうか。経済的な支援と精神的な支援の両方をバランスよく提供することが若者のウェルビーイングの向上に必要不可欠だと考えました。
英国のコミュニティ・プレイ・スペシャリスト、ダイアン・ウートン先生のお話を聞き、遊びの力で在宅で療養する病児とその家族の生活を改善できることを学びました。実際、ダイアンさんは、腫瘍学的疾患と診断された子どもの家族を遊びを通して家庭の幸せの雰囲気を取り戻しながら、子どもへの勇気付けと安心感を与えていました。遊びはあらゆる障壁をなくしてくれます。不安を抱えている子どもや家族にとって普段の生活こそが安心へと繋がっています。そのため、場所や状況が変化しても普段の遊びが出来ることで安心を与えていき、時には活力にもなることが分かりました。遊びが与える影響は多岐に渡りものすごく大きいものだと思いました。
私が1番印象に残っているのは、ダイアン先生の、人生で最も辛く困難な時期にある死を待つ時期にある家族や家庭に招かれることを光栄に思うというお言葉です。まだ未来のあるはずだった子どもが死を宣告されることは、先の見えない暗さばかりがあると思っていましたし、自分にできることが無い無力感ばかりを感じるのでは無いかと思っていました。しかし、ダイアン先生のお話を聞いて、死を待つ子どもであっても、遊びの力で暗い時間を愛と光で満たすことで悲しみを上回る楽しさを感じる事が出来ると知ることが出来ました。これから社会福祉士としてこういった場面に遭遇した時、携われた事を光栄に思い、子ども達が最後まで明るく全力で生きれるように支援していきたいと思いました。
(こどもサミットに参加して)インタビューの中でこどもたちは、仲間といる時、おやつを食べている時、家族といる時が幸せと感じていることを知り、私たちはこの子どもたちの幸せを壊すことの無いよう、関わり続けていくことが大切だと考えました。また、こどもたちが「大人は仕事をしていると大変そうで幸せでなさそう」という意見を口にしているのを見て、これから大人に近づいていくこどもたちが大人になることを恐れないよう、こどもと一緒に幸せを共有する機会を作ることを心がけていき、大人も幸せであることを証明していくことが何より大切だと考えました。
日本の10代の死亡原因の第1位が自殺であることにとても衝撃を受けました。そしてインタビューの中で子どもたちが、大人は幸せそうではない、勉強や仕事が大変そうであると回答しており、子どもたちは、大人のことを思っている以上によく見ているのだと感じました。このように、子どもたちが自分の未来を諦めて閉ざしてしまわないように、大人が子どもたちの声をしっかり受け止める必要があると思いました。そして、大人自身も大変だけれど子どものために無理をして幸せだと伝えていくのではなく、子どもたちと共に心から幸せだと思えるようになることが1番であると思いました。一人ひとりが生きやすく、自然に幸せになれる日々を考えていきたいです。